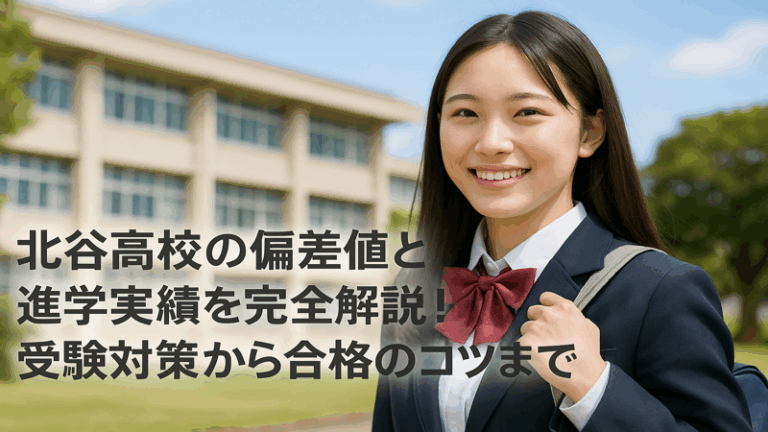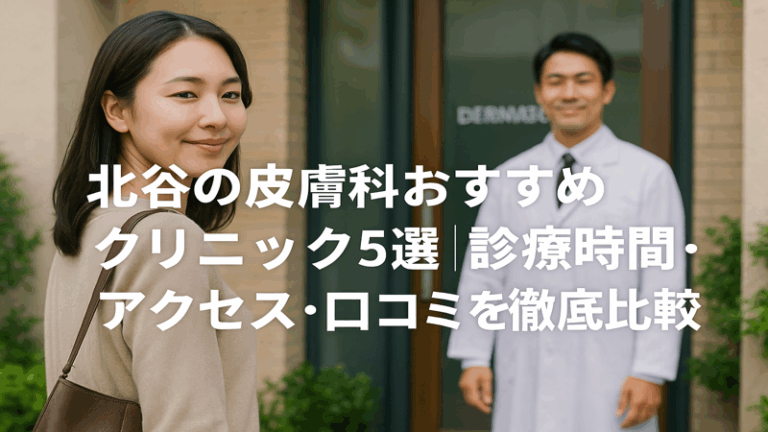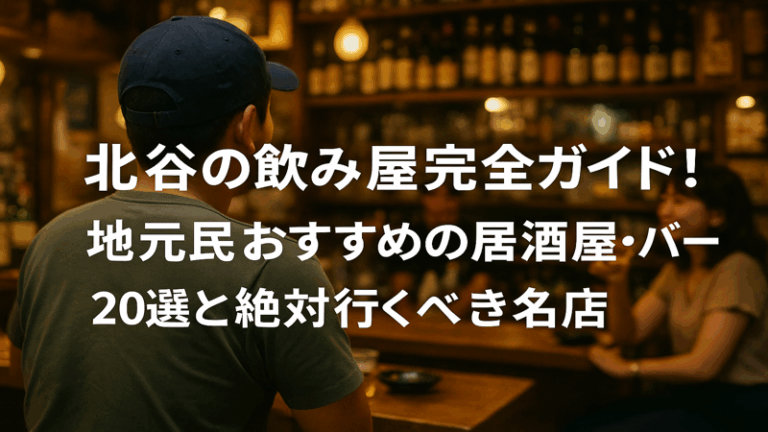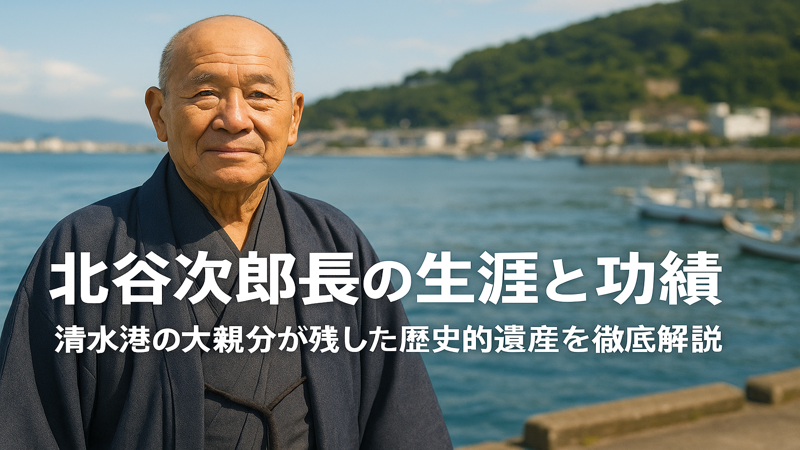
あなたは「清水次郎長って本当に実在した人物なの?」と思ったことはありませんか?結論、清水次郎長は幕末から明治にかけて実在した侠客で、講談や浪曲で語り継がれる以上に波乱万丈な人生を送った歴史上の人物です。この記事を読むことで次郎長の真の姿と彼が現代に残した遺産がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.清水次郎長とは|幕末・明治の侠客として知られる歴史上の人物
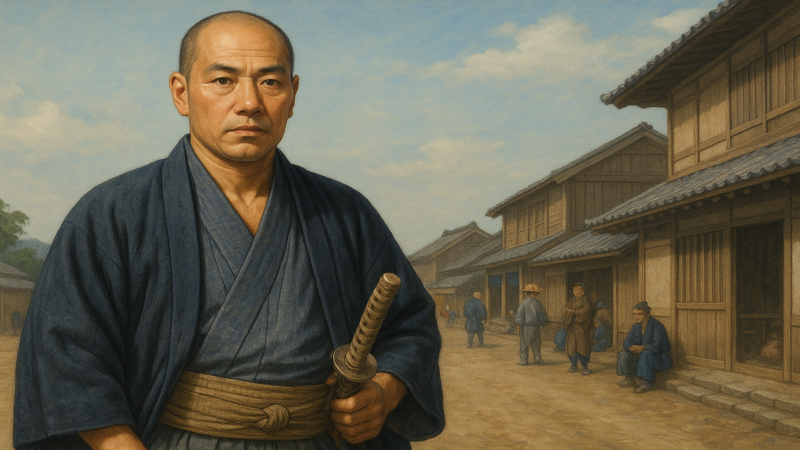
清水次郎長の基本プロフィールと生没年
清水次郎長は文政3年1月1日(1820年2月14日)に駿河国清水港で生まれ、明治26年(1893年)6月12日に73歳で亡くなった幕末・明治期の侠客です。
現在の静岡市清水区にあたる清水港で、船持ち船頭の高木三右衛門の次男として誕生しました。
幼少期から粗暴な性格で手を焼かれ、8歳の時には伯父のもとに預けられるほどでした。
しかし、この荒々しい性格こそが後に「海道一の大親分」と呼ばれる侠客への道筋を作ったのです。
次郎長の人生は大きく4つの時代に分けることができ、それぞれの時代でトップランナーとして活躍しました。
本名は山本長五郎|次郎長と呼ばれるようになった経緯
次郎長の本名は山本長五郎といい、母方の叔父である米問屋・山本次郎八の養子となったことから「次郎長」と呼ばれるようになりました。
「次郎八のところの長五郎」を縮めて「次郎長」という通称が生まれたのです。
養父の次郎八は米穀商「甲田屋」の主人で、実子がいなかったため長五郎を養子に迎えました。
幼少期から周囲の人々が「次郎八のところの長五郎」と呼んでいたため、自然と「次郎長」という呼び名が定着していきました。
この名前こそが、後に全国にその名を轟かせる「清水次郎長」の始まりだったのです。
海道一の大親分として知られた理由
次郎長が「海道一の大親分」と呼ばれたのは、東海道を中心とした広大な縄張りを持ち、義理と人情を重んじる侠客の親分として君臨していたからです。
東は現在の東京から西は滋賀県まで、その勢力は東海道全域に及んでいました。
特に慶応2年(1866年)の伊勢荒神山での大勝負では、圧倒的に不利な状況でありながら勝利を収め、全国にその名を知らしめました。
次郎長は単なる博徒の親分ではなく、困っている人を助け、義理を重んじる人格者としても知られていました。
次郎長が亡くなった際には、乃木大将や福沢諭吉らとともに新聞に「富士を背中にしょって立つ、漢の中の漢一匹」として紹介されるほどの存在でした。
講談・浪曲で広まった次郎長の物語
次郎長の物語が全国的に有名になったのは、講談師・三代目神田伯山と浪曲師・二代目広沢虎造によって語り継がれたからです。
明治17年(1884年)に天田愚庵が著した『東海遊侠伝』が原典となり、これを元に神田伯山が講談『清水次郎長伝』を完成させました。
さらに広沢虎造がこれを浪曲化し、ラジオ放送やレコードで全国に広めたことで、昭和初期の大衆にとって英雄的存在となりました。
「旅行けば駿河の国に茶の香り」で始まる虎造の浪曲は一世を風靡し、次郎長の名前を不動のものにしました。
ただし、講談や浪曲では義理と人情に厚い理想的な侠客として描かれており、史実とは異なる部分も多く含まれています。
2.清水次郎長の生涯|波乱万丈な人生を時代別に解説

幼少期から青年期|米問屋の養子から博徒への転身
次郎長は幼少期から粗暴な性格で知られ、15歳の時に養家から百両を持ち逃げして博徒の道に足を踏み入れました。
文政12年(1829年)、わずか8歳の時にその粗暴な性格に手を焼いた養父によって、由比倉沢の伯父・兵吉のもとに預けられました。
天保5年(1834年)に15歳で養家に戻りましたが、そこで百両という大金を持って逃げ出してしまいます。
しかし、この頃から次郎長の賭博の才能が開花し、持ち逃げした百両を元手に米相場で巨利を博しました。
天保14年(1843年)、博打の際にインチキを発見した次郎長は喧嘩の果てに人を斬り、相手を巴川に投げ込む事件を起こします。
この事件をきっかけに妻と離別し、家業の甲田屋を姉夫婦に譲って無宿人となり、清水の地を離れることになりました。
博徒時代|清水一家を率いて勢力を拡大
次郎長は三河の地で剣術を学んだ後、清水に戻って清水一家を組織し、東海道を舞台に勢力を拡大していきました。
弘化2年(1845年)には伯父の太右衛門と津向文吉の間で起きた出入りを仲裁・調停して治め、調停能力の高さを示しました。
次郎長は単なる暴力に頼るのではなく、交渉術や人望によって問題を解決する能力に長けていました。
清水湊に一家を構えた次郎長は、海上交通や富士川の縄張りを巡って他の親分たちと競い合いました。
次郎長一家は「清水二十八人衆」と呼ばれる優秀な子分たちによって支えられ、その結束の固さは他の追随を許しませんでした。
荒神山の喧嘩|次郎長の名を全国に知らしめた大勝負
慶応2年(1866年)の伊勢荒神山での大勝負は、次郎長の名を全国に轟かせた最も有名な事件です。
神戸の長吉・吉良の仁吉・清水次郎長一家22名が、穴太徳一家と黒駒勝蔵一家を合わせた130余名と対峙しました。
圧倒的に数で劣っていた次郎長側でしたが、敵方が寄せ集めの集団だったため、用心棒が討ち取られると総崩れとなり勝利を収めました。
しかし、この争いで次郎長一家の法印の大五郎と吉良の仁吉が鉄砲で撃たれて死亡する痛手を負いました。
大切な子分を失った次郎長は480名を動員し、長槍170本・鉄砲40丁・米90俵を船に積んで報復に向かいましたが、仲裁が入り大規模な抗争は回避されました。
この一連の事件により「清水次郎長」の名は全国に知れ渡り、海道一の大親分としての地位を確立したのです。
明治維新後|実業家・社会事業家としての活動
明治維新を迎えると、次郎長は博徒から実業家・社会事業家へと転身し、新しい時代に適応していきました。
慶応4年(1868年)、東征大総督府から街道警護役(警察署長)への就任を打診されましたが、次郎長は「罪逃れのために役人になったと笑われる」として辞退しました。
同年、旧幕府方の咸臨丸が清水港で新政府軍の攻撃を受けた際、次郎長は死者を手厚く葬り、この義侠心が山岡鉄舟や榎本武揚との知己につながりました。
維新後は富士山麓の開墾事業に乗り出し、旧幕臣の救済と新田開発に取り組みました。
また、清水港の海運業にも参入し、地域の発展に大きく貢献しました。
晩年の生活と死去まで
次郎長は晩年、船宿「末廣」を経営しながら社会事業に力を注ぎ、明治26年(1893年)に73歳で生涯を閉じました。
明治時代の次郎長は、かつての博徒の親分から地域の名士へと変貌を遂げていました。
茶業の発展にも関わり、静岡県が茶処として栄える基盤作りにも一役買いました。
次郎長は3度結婚しましたが、3人の妻はすべて「お蝶」と呼ばれていました。
死去の際には多くの人々に惜しまれ、現在も清水区の梅蔭禅寺に眠っています。
3.清水次郎長の功績と歴史的遺産|現代に残る影響

咸臨丸事件での義侠心|山岡鉄舟との出会い
慶応4年(1868年)の咸臨丸事件は、次郎長の義侠心を示す最も有名なエピソードで、これがきっかけで山岡鉄舟との運命的な出会いが生まれました。
戊辰戦争の際、修理のため清水港に立ち寄った咸臨丸が「逆賊船」として放置され、乗組員の遺体が船内に残されていました。
新政府軍に殺された乗組員の遺体を、次郎長は小舟を出して収容し、丁重に葬ったのです。
この義侠心に深く感動した幕臣の山岡鉄舟が次郎長のもとを訪れ、生涯にわたる友情が始まりました。
山岡鉄舟との出会いは、次郎長が単なる博徒から社会事業家へと転身するきっかけとなった重要な出来事でした。
富士山麓の開墾事業|社会事業家としての貢献
次郎長は明治維新後、山岡鉄舟の勧めで富士山麓の開墾事業に取り組み、旧幕臣の救済と新田開発という社会事業に大きく貢献しました。
この開墾事業は、職を失った旧幕臣たちに新しい生活の場を提供する重要な意味を持っていました。
次郎長は自らの人脈と資金を投じて、荒れ地を農地に変える大規模な開発を進めました。
開墾された土地では茶の栽培も行われ、後の静岡茶の発展にもつながりました。
この事業により、次郎長は単なる侠客から社会事業家として新たな評価を得ることになりました。
清水港の発展への貢献|海運業での活躍
次郎長は海運業にも参入し、清水港の近代化と発展に大きく貢献しました。
船宿「末廣」の経営を通じて、清水港を利用する船舶の便宜を図りました。
また、港湾設備の改良や海運ルートの開拓にも積極的に取り組みました。
次郎長の海運業への取り組みは、清水港が東海地方の重要な港湾として発展する基盤となりました。
現在の清水港の繁栄には、次郎長の先見性と努力が大きく寄与していると言えるでしょう。
現代に残る次郎長ゆかりの史跡と文化財
現在も静岡市清水区には次郎長ゆかりの史跡が数多く残されており、その歴史的価値が認められ保存されています。
次郎長生家は2018年3月に国の登録有形文化財に登録され、2017年7月に耐震改修工事を経てリニューアルオープンしました。
梅蔭禅寺には次郎長、お蝶、大政、小政の墓があり、次郎長の銅像も建てられています。
興味深いことに、次郎長の墓石は「博打に勝つお守りになる」という噂が立ち、墓石を少しずつ砕いて持ち帰る人が絶えませんでした。
次郎長通りという商店街もあり、次郎長が使った道具類や資料などが展示され、観光名所として親しまれています。
4.清水次郎長と清水二十八人衆|有名な子分たちの物語
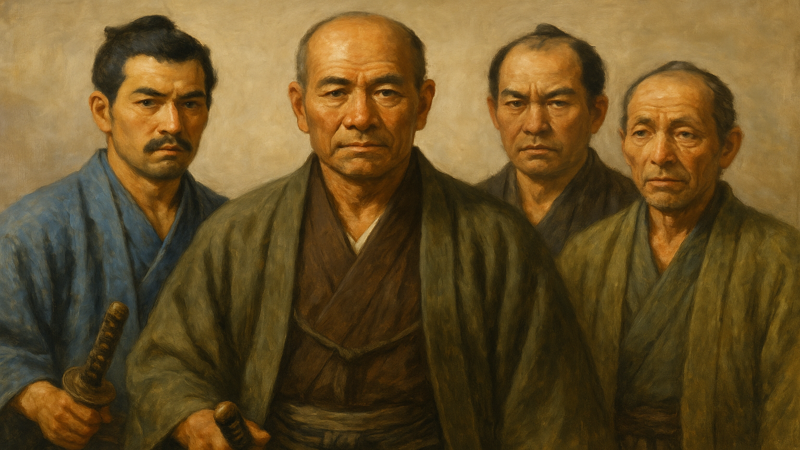
森の石松|最も有名な子分の実像と物語
森の石松は清水二十八人衆の中で最も有名な子分で、「寿司食いねぇ」の名台詞で知られていますが、実際の石松は講談で描かれるほど単純な人物ではありませんでした。
石松の本名は不詳で、遠州森町(現在の静岡県周智郡森町)の出身とされています。
講談や浪曲では純朴で一本気な性格として描かれていますが、実際は次郎長に重用される優秀な子分でした。
石松は次郎長一家の中でも特に信頼され、重要な任務を任されることが多かったのです。
残念ながら石松は若くして亡くなりましたが、その忠義は次郎長によって深く愛され、後世まで語り継がれることになりました。
大政・小政兄弟|次郎長を支えた忠実な部下
大政・小政兄弟は次郎長一家の中核を担う重要な子分で、次郎長の片腕として活躍しました。
兄の大政は沈着冷静な性格で、次郎長の参謀的な役割を果たしていました。
弟の小政は行動力があり、実働部隊のリーダーとして活躍しました。
兄弟は次郎長に対する忠義が厚く、最後まで次郎長と運命を共にしました。
現在も梅蔭禅寺には次郎長とともに大政・小政の墓が建てられており、三人の深い絆を物語っています。
その他の主要な子分たち|都鳥の吉兵衛・追分三五郎など
清水二十八人衆には他にも個性豊かな子分たちがおり、それぞれが次郎長一家を支える重要な役割を果たしていました。
都鳥の吉兵衛は知略に長けた子分で、次郎長の戦略を練る際の重要なアドバイザーでした。
追分三五郎は講談で創作された架空の人物ですが、実在のモデルとなった人物がいたとされています。
法印の大五郎は荒神山の喧嘩で命を落としましたが、次郎長が最も信頼していた子分の一人でした。
これらの子分たちの存在があったからこそ、次郎長は海道一の大親分として君臨することができたのです。
まとめ
清水次郎長について分かったポイントをまとめると以下の通りです。
• 清水次郎長は1820年生まれの実在の人物で、幕末・明治期の侠客として活躍した
• 本名は山本長五郎で、養父の次郎八から「次郎長」の通称が生まれた
• 荒神山の喧嘩で勝利を収め、「海道一の大親分」としての地位を確立した
• 咸臨丸事件での義侠心により山岡鉄舟と出会い、人生の転機を迎えた
• 明治維新後は実業家・社会事業家として富士山麓の開墾や海運業に取り組んだ
• 講談師・神田伯山と浪曲師・広沢虎造により全国的な人気を獲得した
• 清水二十八人衆と呼ばれる優秀な子分たちに支えられていた
• 現在も清水区には生家や墓所など多くの史跡が残されている
• 単なる博徒ではなく、義理人情に厚い人格者として慕われていた
• 清水港の発展や静岡茶の振興にも貢献した地域の恩人でもあった
清水次郎長は単なる講談の主人公ではなく、激動の時代を生き抜いた実在の人物であり、その波乱万丈な生涯は現代に多くの教訓を与えてくれます。義理と人情を重んじ、時代の変化に適応しながら社会に貢献した次郎長の生き方は、現代を生きる私たちにとっても学ぶべき点が多いのではないでしょうか。